2014年に公開されたハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』。本作は同一世界観のクロスオーバー作品として扱うモンスターバースシリーズとして第1作目の作品で、その続編となる第2作目が2019年5月31日に公開された『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』です。
YoutubeのWarner Bros. Pictures公式チャンネル の最終予告映像はこちら。
キングギドラ、モスラ、ラドンが登場
『GODZILLA ゴジラ』ではオリジナルの怪獣ムートーが登場し、ゴジラと壮絶なバトルを繰り広げました。
続編となる『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』では円谷作品でもおなじみのキングギドラ、モスラ、ラドンが登場し、ゴジラも交えた四大怪獣が壮絶なバトルを繰り広げます。
CGで製作されたハリウッド版キングキドラ、モスラ、ラドン。日本製の着ぐるみとは違い、圧倒的な迫力と美しさ。劇場の巨大スクリーンで鑑賞しましたが、圧倒されてしまいました。
初めて四大怪獣が登場した円谷作品を振り返る
1954年 作品『ゴジラ』
日本で『ゴジラ』が公開されたのは1954年(昭和29年)。
カラー作品ではなく、モノクロ映像です。
日本初の本格SF怪獣映画で、監督は本多猪四郎、特撮を担当したのは円谷英二。
『ゴジラ』の前は太平洋戦争を題材とした作品で、戦闘機や戦艦などの特撮部分を担当していました。
当時社会問題となっていたアメリカのビキニ環礁の水爆実験に着想を得て、放射能の影響で体長50メートルの巨大怪獣ゴジラが誕生しました。
本作は1953年にアメリカで公開された『原子怪獣現る』に大きな影響を受け、水爆で誕生したゴジラが東京に上陸し、街を破壊しつくすというストーリー。
アマゾンプライムビデオ
ゴジラ
日本怪獣特撮の特徴である着ぐるみ
『原子怪獣現る』はストップモーションアニメーションの第一人者であるレイ・ハリーハウゼンが特撮を担当し、怪獣の動きは1枚1枚の画像の繋ぎ合わせたアニメーションで作られています。
ゴジラの特撮を担当した円谷英二は当初、ハリーハウゼンと同じようなストップモーションアニメーションで動きを作ろうとしていましたが、膨大な時間と費用がかかることから断念。
俳優に着ぐるみを着せて怪獣を演じさせることになりました。
日本独特の手法である着ぐるみ怪獣の登場です。
着ぐるみ俳優/中島春雄
着ぐるみに入って演技をしたのは中島春雄で、のちにゴジラの他、ラドン、メガヌロン(映画『ラドン』に登場)、モゲラ、バラン、モスラの幼虫、マグマ、バラゴンなど円谷怪獣作品の着ぐるみ俳優として活躍しました。
『ゴジラ』は空前の大ヒット、続編シリーズ化
『ゴジラ』は観客動員数961万人という空前の大ヒット作となり、当時経営が傾いていた東宝を立て直すほどの興行収入となりました。
本作のヒットを受けてすぐに続編『ゴジラの逆襲』が制作されました。この作品にはアンギラスという怪獣が登場し、大阪市街でゴジラとの闘いシーンが描かれました。
怪獣バトルが初めて描かれることになった作品です。
1956年『空の大怪獣ラドン』
1955年『ゴジラの逆襲』が公開された翌年、古代翼竜を怪獣にした『空の大怪獣ラドン』が公開されました。
東宝怪獣映画初のカラー作品。
アマゾンプライムビデオ
空の大怪獣 ラドン
舞台は福岡にある炭鉱で、落盤事故をきっかけとしてラドンが登場します。
空中を高速で飛ぶラドンが巻き起こす突風シーンが圧巻
本作の見所はラドンが空中を高速で飛ぶ際に巻き起こす突風シーンでしょう。
福岡市街が突風により破壊される様子は圧巻です。
ラドンはゴジラのように口から光線を吐いたりするような武器はなく、唯一あるのは巨大な翼が巻き起こす突風のみ。
しかし、その破壊力はすさまじいです。
ビルの壁が紙のように剥がれ落ち、車や電車が空中に舞い上がる。
特に当時完成したばかりの西海橋がラドンの衝撃波で崩れ落ちていくシーンはミニチュアとはいえかなりの迫力があります。
『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』予告映像にもラドンが起こしたと思われる突風シーンが確認できます。
1961年『モスラ』
ゴジラ、ラドンに続く三番目の怪獣キャラクターとして登場したモスラ。
巨大な蛾の姿をした怪獣で、巨大な翅を羽ばたかせて飛翔します。
ラドンと同じように翅から繰り出す衝撃波が武器で、イモムシ状の幼虫の時期は口から毒糸を吹き出し、相手を窒息死させます。

モスラ(1961)
本作は『ゴジラ』と同じように水爆実験がストーリーの背景にありますが、モスラは水爆の影響で巨大化したという設定ではなく、水爆実験の影響から実験場となった島の住民たちを守っていた守護神ということになっています。
守護神モスラとテレパシーで意思を通じ合う双子の小美人が登場
本作は企画の段階で、女性でも観られる怪獣映画という案が出されたことで、モスラより先に小美人の設定が生まれました。
小美人を演じたのは当時人気姉妹歌手グループであったザ・ピーナッツ(伊藤エミ、伊藤ユミ)で、劇中で彼女らが歌った「モスラの歌」はヒットしました。
モスラーヤ モスラー ドゥンガン カサクヤン インドゥムウ
インドネシア語を参考にした歌詞らしいのですが、さだかではありません。
モスラの幼虫が東京タワーを柱に繭を作るシーンは圧巻
円谷特撮の特徴として、リアルな市街地模型があげられますが、本作でもリアルに東京の街が再現されています。
蛾がイモムシから成虫になる過程に繭を作りますが、モスラも成虫になるために繭を作ります。
その繭を作った場所がなんと東京タワー。
東京タワーを圧し折り、それを柱にして繭を作るのです。
特撮で映像化されたシーンは圧巻です。
『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』でも幼虫が登場するのか?登場するなら繭は作るのか?気になりますね。
本作のあとモスラは1964年公開の『モスラ対ゴジラ』でゴジラと戦うことになります。
モスラはゴジラに次いで円谷怪獣の人気キャラクターとなり、以降のゴジラシリーズに何度も登場し、単独作品でも1996年にリメイクされた『モスラ』、1997年『モスラ2 海底の大決戦』、1998年『モスラ3 キングギドラ来襲』と3年続けて公開されました。
アマゾンプライムビデオ
モスラ
1964年『三大怪獣 地上最大の決戦』
宇宙怪獣キングギドラが初登場
ゴジラ、ラドン、モスラという三大怪獣を世に出し成功した東宝円谷がキングギドラという宇宙怪獣を登場させ三大怪獣と戦わせた作品。
実は本記事のタイトルには四大怪獣としているのですが、公式には四大怪獣とは呼ばず、ゴジラ、ラドン、モスラの三匹で三大怪獣と呼んでいます。
キングギドラは怪獣には含まれていないのか?なんて疑問もあるのですが。
ゴジラ、ラドン、モスラの有名三大怪獣が地球を破壊に来た宇宙怪獣キングギドラを共同でやっつける、という意味のタイトルなのでしょう。
キングギドラはその後、東宝怪獣作品には頻繁に登場し、ゴジラ、ラドン、モスラと並ぶ有名怪獣になっていますので、四大怪獣と呼んでもいいんじゃないかと思います。
アマゾンプライムビデオ
三大怪獣 地球最大の決戦
造形のモデルはヤマタノオロチ
キングギドラの造形は1959年東宝作品『日本誕生』に登場したヤマタノオロチが元になっています。
アマゾンプライムビデオ
日本誕生
三つの長い首を支える太い胴体には薄い膜状の翼と2本の尾を持ち、口からは稲妻のような引力光線を吐きます。
胴体部分はスーツアクターが入る着ぐるみとなっていますが、三つの長い首、二つの翼、尾はピアノ線で操作しています。
この操作には25名前後の人員を要したとか。
本作でのキングギドラは金星から来た宇宙怪獣という設定で、金星文明を壊滅させたあと、地球に飛来してきました。
本作以降、ゴジラシリーズとモスラシリーズに登場してきますが、シリーズ中最強のヴィランと言ってもいいでしょう。
ゴジラが人間の味方になったきっかけになった作品
キングギドラを倒すため、モスラの説得でゴジラとラドンが共闘します。
本作からゴジラが人間の味方という設定になり、1975年公開の『メカゴジラの逆襲』までそれが続きます。
本作を境にゴジラ映画がお子様向けになっていったような気がします。
最期に
『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』 は本作が原案になっていると思われますが、ストーリーも大きく異なるでしょうし、それぞれの怪獣の設定にも独自の変更が加えられていることでしょう。
円谷怪獣ファンにとってはあまり大きな変更がないことを期待するでしょうが、『ゴジラ』が公開されてから65周年となるこの年に最新映像技術を駆使した迫力ある四大怪獣が観られることは本当に嬉しい限りです。







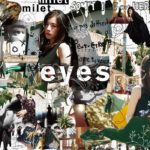

コメント